今回は、先日、Webストアに追加したケネディ大統領記念封筒に関連して、ケネディ大統領の就任式について紹介致します。
以下は、英語版WekipediaのInauguration of John F. Kennedyの説明の一部を訳したものです。
ジョン F. ケネディ 大統領就任演説
1961年1月20日、John F. Kennedyは第35代のアメリカ合衆国大統領に就任しました。就任式当日の1961年1月20日のワシントンは、大雪がふり(吹雪となり)混乱が生じて就任パレードは危うく中止されるところでした。
陸軍は道路の除雪等にあたりました。31代大統領のハーバート・フーバーは、ワシントンに着陸する事ができず、就任式を欠席しました。翌日、全大統領のドゥワイト・アイゼンハワー前大統領と一緒に議会へ行く前に、ケネディはジョージタウンにあるホーリー・トリニティ・カソリック教会の朝のミサに出席しました。分厚い巨大なコートとスカーフを身につけた前大統領と比べて、彼の若くて逞しいところを見せるためケネディは外套は一切着用しませんでした。
ケネディ大統領の就任演説は、歴史研究家の間で、アメリカの歴史上、最も素晴らしい演説の一つであったと認識されています。当時、冷戦(the Cold War)がくすぶっており、国内では公民権の問題やその他の社会的改革の訴えが盛り上がっている中での大統領就任演説でした。

1961年1月20日金曜日、午後12時51分にケネディは演説は大統領就任の宣誓をし、その後、演説を行いました。
演説は1364語で最初の言葉から最後まで途中の拍手の間の13分と42秒かかりました。これは、歴代で4番目に短い大統領就任演説でした。本演説は初めてカラーでテレビ放送された大統領就任演説でした。アメリカの歴史上、最も優れた大統領演説であったと広く世間に認知されています。
ドラフト(草稿・原稿)の作成
演説の原稿は、ケネディと彼のスピーチライターのTed Sorensonによって作成されました。ケネディはソレンソンにアブラハムリンカーンのGettysburg演説(南北戦争中の1863年11月19日にリンカーンがゲッツィーバーグで行ったアメリカの歴史上最も良く知られた演説の一つ。)と他の大統領就任演説について調べる様に依頼しました。
ケネディは、1960年の11月の終わりから、就任演説の概念やアイディアを集め始めました。また、彼は様々な人々から助言を得ました。ケネディは、ハーバードのエコノミストのJohn Kenneth Galbraithと前民主党大統領候補のAdlai Stevensonの提案のいくつかを彼の演説に取り入れました。
ケネディの演説の一節、”Let us never negotiate out of fear. But let us never fear to negotiate.”はGalbraithの提案した”We shall never negotiate out of fear. But we shall never fear to negotiate”とほぼ同じです。Stevensonの提案した”if the free way of life doesn’t help the many poor of this world it will never save the few rich.”は、ケネディの演説の一節、”If a free society cannot help the many who are poor, it cannot save the few who are rich.”の元となっています。
演説(スピーチ)のメインアイディア
冷戦による米ソ関係東西陣営の勢力争いの緊張が高まる中で就任する大統領として、アメリカの国力を代表し、同時に平和的関係の継続に取り組むと言う、非常に困難であると思われる職務を遂行できる力を持っていることを認知されることが念頭にありました。
就任演説は大統領の任期においての包括的な目標についてが、ほとんどとなりました。ケネディは核の力と兵器開発の競争が加速していることによる危機が高まっている事を強調し、純粋な兵器による力へ注力するのではなく、代わって国際的関係の継続と世界の貧困の改善に力を注ぐべきであることが重要である事をメインポイントしていました。
これらの事を元に、演説のメインゴールは、当時のパニックと懸念が常時沸き起こっている中、明るい未来とアイディアリズムを強調したものとなりました。
雄弁的要素(Rhetorical Elements)
スピーチの主な焦点は、”職務と力の関係”の一つのテーマに絞られていました。これはスピーチの最初のパートにおいて、ケネディが使用したj”juxtaposition(並置)”を強めたところで強調されています。
例として、彼はスピーチの第2段落で、”…Man holds in his mortal hands the power to abolish all forms of human poverty and all forms of human life,”(注:下に大統領演説の和訳を引用します。第二段落の該当箇所を太字にしています。)は、アメリカだけでなく他の国々もその力を持っている事を明示し冷戦の重要事項がどこにあるのかを示しました。
そして、彼は再びその戦略を第五段落で使用しています。”United there is little we cannot do in a host of cooperative adventures. Divided there is little we can do,”(この該当箇所も太字にしています。)、国際社会の価値に再び焦点を向けるべきだと言う考えを再び伝えています。
古典的な雄弁術の一つの主要部である適切化(prepon(the apropriate))は、このスピーチの随所に見られます。冷戦が始まってからアメリカの人民に恐怖と不安が広がっている事を認め、ケネディは明るい見方とアイディアリスティクのトーンで安堵を与えるスピーチにギアを移します。
彼は素早くスピーチを将来に向け、”Let both sides…”によって、彼が緊張関係に対して国際的協調が最終目標である事を訴えることで対処する計画であることを暗示しています。
彼は、ネガティブなアイディアについてもそれが好機となり挑戦であると言ったアメリカ人の本質的な考えに訴える態度をとっています。第4段落の次に引用する最後の言葉にこれが非常に強く示されています。”In the long history of the world, only a few generations have been granted the role of defending freedom in its hour of maximum danger,”アメリカの民衆におびえさせるのではなく、挑戦する気持ちにさせるシンプルでひねった言葉です。
最後にジョン F. ケネディの就任演説での彼の有名な発言について触れないわけには行きません。”ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country.” (該当部を太字にしています。)
大統領就任演説全文和訳
JOHN F. KENNEDY PRESIDENTIAL LIBRARY AND MUSEUMの”ジョン・F・ケネディ大統領新任演説から引用。
米国連邦議会議事堂
ワシントンD.C.
1961年1月20日
ジョンソン副大統領、下院議長、最高裁判所長官、アイゼンハワー大統領、ニクソン副大統領、トルーマン大統領、聖職者諸賢、そして国民の皆さん。
今日のこの日を、政党の勝利ではなく、自由を讃える機会として祝福しましょう。これは終わりと始まりの象徴であり、再生と変革の兆しです。なぜなら、私が先ほど皆さんと全能の神の前で誓った言葉は、我々の父祖がおよそ175年前に定めた厳粛な誓いと同じものだからです。
世界は大きく様変わりしました。今日の我々は、あらゆる形の貧困を撲滅する力と、あらゆる形の人間の生命を根絶させる力の両方を、神ならぬこの手に持っています。しかしながら、かつて我々の父祖がそのために戦った革命的な信条、つまり、人間の権利は国家の寛大さによって与えられるものではなく、神から授けられたものであるという信条は、今もなお世界各地で争点となり続けています。
我々は、その最初の革命の継承者であることを忘れてはなりません。今このとき、この場所から、敵味方の区別なく、すべての人に伝えましょう。たいまつはアメリカの新しい世代に渡されました。20世紀に生まれ、戦争で鍛えられ、苦しく困難な平和に身を置き、古来の伝統に誇りを持つ我々は、人間の権利が徐々に奪われていくのを見過ごすことはできません。人権こそ、この国の変わらぬ関心の対象であり、今日の我々が国の内外を問わず力を注いでいるものです。
すべての国々に知らせましょう。アメリカに好意を持つ国にも、そうでない国にも。我々はあらゆる代償を支払い、あらゆる重荷を担い、あらゆる困難に耐え、すべての友を支え、自由の存続と繁栄を妨げるすべての敵と戦う覚悟であるということを。
我々はこれを固く誓います。そして、それだけにとどまりません。
文化的・精神的な源を共有する古くからの盟友に対し、我々は誠実な友として忠誠を誓います。団結しましょう。我々が何度も協力して取り組めば、できないことはないはずです。分裂していれば、できることはほとんどありません。対立し、ばらばらに分裂した状態では、難しい課題に立ち向かうこともできません。
これから新たに自由主義世界に迎える国々に対しては、植民地支配という1つの形が終わり、その代わりにもっと過酷な鉄の専制が始まるという事態にはならないことを約束します。我々の考えがいつも支持されるとは期待していません。ただ、彼らが自らの自由を強く求めること、そして、虎にまたがって権力を握ろうとする者は結局虎に喰われるという昔からの教訓を忘れないことを願っています。
世界の人口の半分を占める、集団的困窮から抜け出そうと懸命にもがいている人々に対しては、彼らの自助努力を支援すべく最大限の努力をすることを誓います。どれだけ長い期間かかるとしてもです。これは共産主義者がそうしているからでも、票集めを狙っているからでもなく、ただそれが正しいことだからです。もし自由な社会で多数の貧困者を救うことができなければ、少数の富裕者を救うこともできません。
国境の南に位置する同朋諸国に対しては、特別な誓いを立てましょう。有言実行を実践すべく、発展のための新しい同盟を結び、自由な民衆と自由な政府が貧困の連鎖から抜け出せるように尽力することを誓います。しかし、この平和的革命の希望が敵対勢力によって絶たれるようなことがあってはなりません。 すべての近隣諸国に伝えねばなりません。我々は南北アメリカ大陸のどこで侵略行為や政権転覆の企みがあったとしても、それに一致協力して対抗する心構えであるということを。そして、他の大国すべてに知らしめましょう。この大陸は自らの領土を自ら支配するのだということを。
世界中の主権国家の集まりである国連は、戦争の手段が平和の手段をはるかに凌駕しているこの時代において、最後に残された希望の光です。我々は国連をただの罵り合いの場にするのではなく、新しい国や弱い国の盾とするべく努め、国連憲章の及ぶ地域が増えるように力を尽くすことを改めて誓います。
最後に、我々に敵対する国家に対しては、誓約ではなく要請をしたいと思います。双方で新たに平和への道を進もうではないかと。科学によって解き放たれた破壊的な力が、意図的にせよ偶発的にせよ、人類を自滅に追い込む前に。
これは弱さからの要請ではありません。我々の軍備が十分であると確信しているからこそ、どうしても軍備を使用すべきでないと確信できるのです。
しかし現在のあり方では、二大陣営のどちらも安心することはできません。どちらの陣営も近代兵器の費用負担に苦しみ、核兵器の着実な拡散に恐れを抱きながらも、人類の最終戦争を食い止めている不安定な恐怖の均衡を崩そうと競争しているのです。
共に新しく始めようではありませんか。礼儀正しい振る舞いは弱さの証しではなく、誠実さは証明すべきものだということを共に心に刻みながら。 恐怖ゆえに交渉してはなりません。しかし、交渉することを恐れてはなりません。
共に考えましょう。我々が団結できる問題は何かを。互いに意見の異なる問題にいつまでもこだわるのではなく。
共に作り上げましょう。兵器の査察と規制に関する初めての本格的かつ詳細な提言を。そして、他国を破壊できる絶対的な力を、すべての国々の絶対的な管理下に置きましょう。
共に努めましょう。科学の恐怖ではなく科学の素晴らしさを呼び覚ますために。互いに力を合わせ、宇宙を探査し、砂漠を征服し、病気を根絶し、深海を開発し、芸術と商業を奨励しましょう。
共に手を取りましょう。預言者イザヤが語った、「くびきの結び目をほどいて虐げられた人を解放し」という言葉が地球上のあらゆる場所で聞かれるように。
そして、もしも双方の協力を足がかりとして不信感を拭うことができたら、新たな勢力均衡を図る代わりに、共に新しい試みに取り組みましょう。それは、法に基づく新しい世界、つまり強い者が法を守り、弱い者が保護され、平和が維持されている世界を作ることです。
このすべてを、最初の100日間で達成することはできないでしょう。1000日でも難しいでしょうし、この在任期間中、あるいはこの地上に我々が生きている間には達成できないかもしれません。それでも、始めようではありませんか。
国民の皆さん、我々の進む道が最終的に成功するか失敗するかは、私自身よりも皆さんにかかっています。建国以来、アメリカの各世代の人々は国家への忠誠の証しとして召集を受けてきました。この召集に応えた若者たちの墓が世界各地に点在しています。
今、我々を召集するラッパが再び鳴り響いています。これは、武器を取れという合図ではありません。戦いの合図でもありません。ただ、我々は武器を用意し、陣容を整えておく必要があります。これは、長く先の見えない戦いの重荷を担えという呼びかけなのです。来る年も来る年も、希望をもって喜びとし、苦難を耐え忍びながら、人類共通の敵である虐政、貧困、病気、そして戦争そのものとの戦いを貫く覚悟が求められています。
これらの敵に対し、世界の東西南北にわたる大同盟を組んで当たり、すべての人の暮らしをいっそう実り豊かなものにすることはできないでしょうか。この歴史的な試みに、皆さんもご参加いただけないでしょうか。
世界の長い歴史の中で、自由が最大の危機に晒されているときに、それを守る役回りを与えられた世代というのは多くありません。私はこの責任を恐れず、喜んで受け入れます。おそらく皆さんも、この役目を他の誰かや他の世代に譲りたいとは思わないでしょう。我々がこの取り組みに注ぎ込む精力と信念、そして献身的な努力は、この国とこの国に奉仕する人々を明るく照らし、その情熱の光は世界を輝かせるはずです。
そして、同胞であるアメリカ市民の皆さん、国があなたのために何をしてくれるかではなく、あなたが国のために何ができるかを考えようではありませんか。
また同胞である世界市民の皆さん、アメリカがあなたのために何をしてくれるかではなく、人類の自由のために共に何ができるかを考えようではありませんか。
最後に、アメリカ市民の皆さんも世界市民の皆さんも、どうぞ我々が皆さんに求めるのと同じ水準の熱意と犠牲を我々に求めてください。良心の喜びを唯一の確かな報酬とし、歴史が我々の行いに正しい審判を下してくれることを信じて、この愛する世界を導いていこうではありませんか。神の祝福とご加護を願いつつ、この地上で神の御業が真に我々のものになることを念じて。
後記
さすがに歴史上、最も素晴らしい大統領就任演説と言われるだけのことはあるなと思いました。ちょっと面白いなと思ったのは、YouTubeで、共和党支持者の人達が「彼の演説はまさに共和党大統領そのものだ1」とのコメントが多くありました。
雄弁的要素の説明にありますが、否定的な事も肯定的にできるための好機であり、それに対して挑戦するのが我々の務めだと言う論理展開の手法は、アメリカ人の本質的な概念、考え方をうまくついています。
この様なところも大きなところでのアメリカの文化、思考を代表して示していると思います。
尚、上の大統領演説の訳も私のWikipediaの訳もかなり意訳が入っています。
ここまで読んで下さった方、長文におつき合い下さいまして、ありがとうございました。

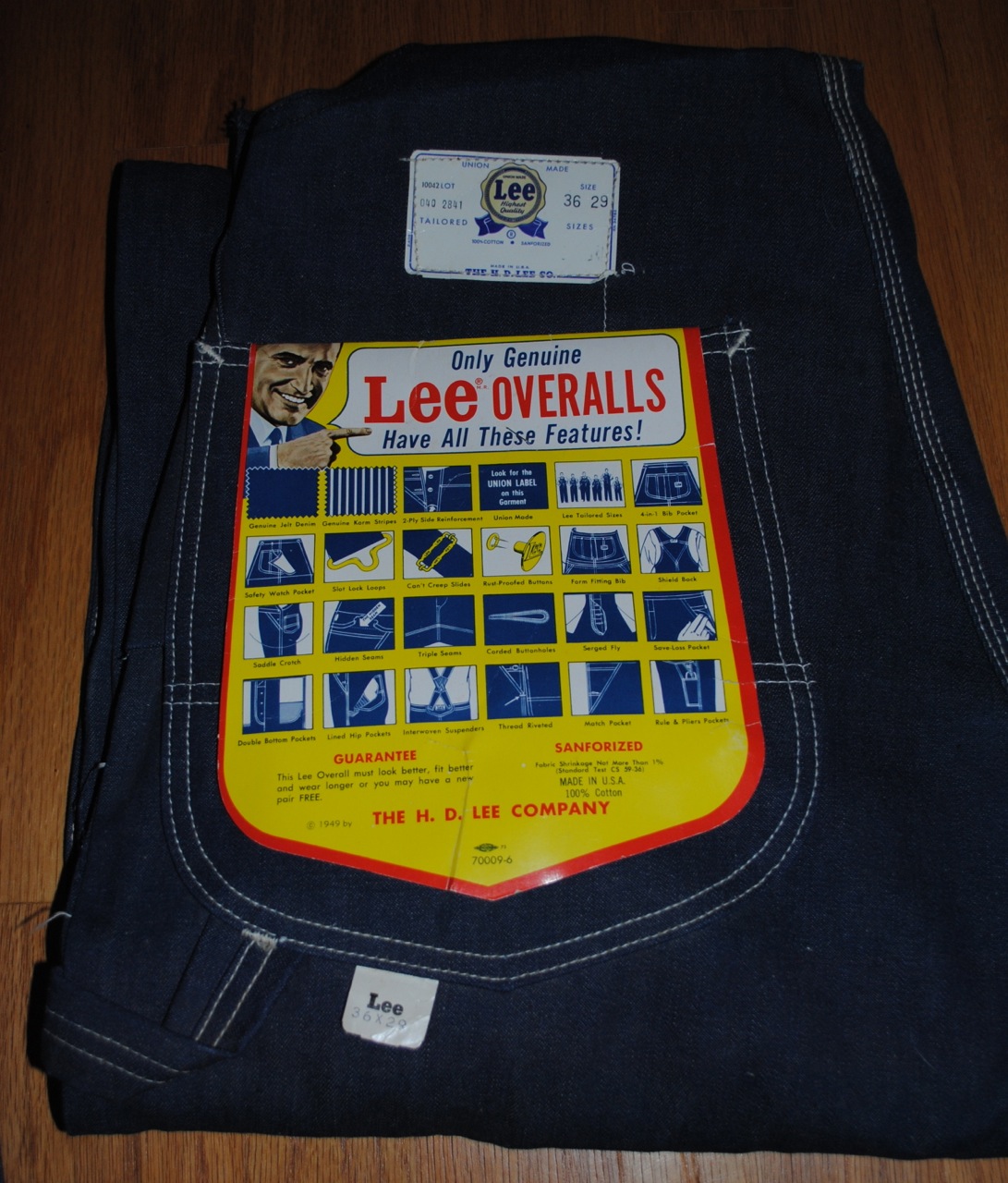
コメントを残す